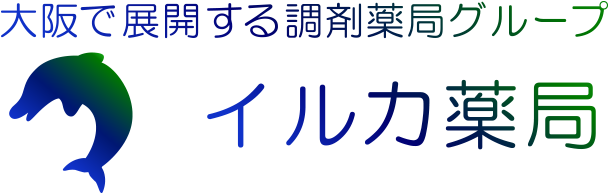糖尿病とは、血糖値(血液中に含まれるブドウ糖)が慢性的に高くなる病気のことです。
日本人の10人に1人が発症しているといわれ、放置すれば末梢神経がピリピリと痛み出し、目の血管も糖に侵され網膜症も進みます。
最悪の場合は失明することもあり、脳卒中・心筋梗塞などの発症、手足が腐って切断を余儀なくされることもある恐ろしい病気です。
初期の糖尿病は自覚症状がなく、「サイレントキラー」とも呼ばれています。
私たちの体にとって、糖分(ブドウ糖)は重要なエネルギー源です。
食事から摂取された糖分は血液によって全身の細胞に運ばれ、生命活動を支えています。
しかし、何らかの原因で血液中の糖分が過剰になり、その状態が慢性的に続くと、体を蝕む「毒」としての側面を見せ始めます。
持続的な高血糖が引き起こす最大の問題は「血管へのダメージ」です。
血液中に余計な糖分が多いと、血管の内壁を構成するタンパク質と結びつき、「糖化反応」という現象を引き起こします。
この糖化反応によって、血管は弾力性を失い、硬く脆くなり、動脈硬化が進んでしまうのです。
当然ながら太い血管で動脈硬化が進めば、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気のリスクが高まります。
さらに高血糖の影響は、毛細血管のような細い血管にも及びます。
毛細血管が密集している腎臓・網膜・末梢神経はダメージを受けやすく、いずれ糖尿病の三大合併症になってしまいます。
糖尿病の三大合併症とは、糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害をいいます。
糖尿病性腎症は、腎臓のフィルター機能が損なわれ、進行すると人工透析が必要になります。
糖尿病性網膜症は、網膜の血管がダメージを受け、視力低下や失明に至る可能性があります。
糖尿病性神経障害は、手足の先にピリピリとした痛みや痺れが現れ、感覚が鈍くなります。
さらに重症化すると足の壊疽を引き起こし、切断に至るケースもあります。
さらに持続的な高血糖の状態は、免疫機能の低下を招き、感染症にかかりやすくなったり、傷が治りにくくなったりします。
また、歯周病を悪化させることも知られています。
血液は全身を巡っているため、持続的な高血糖は、いわば全身の細胞や組織が常に過剰な糖分に晒されている状態を意味します。
だからこそ、糖尿病は「全身病」と呼ばれるのです。
生活習慣の乱れが発症に大きく関与している2型糖尿病では、第一に原因となる食生活や運動習慣の乱れを正す生活指導が行われます。
重症な場合を除き、1~2か月ほど生活改善を行ったうえで薬物療法など次のステップの治療に進むか否かを判断するのが一般的です。
一方、糖尿病の中には免疫のはたらきの異常により、インスリンを産生する膵臓の細胞が破壊されることで発症するタイプもあります。
このタイプは「1型糖尿病」と呼ばれ、生活習慣の乱れなどは発症に関与しないものの、明確な発症メカニズムは解明されていません。
生活改善などを行っても血糖値が十分に下がらない場合は、血糖値を下げる薬による薬物療法が行われます。
血糖値を下げる薬にはいくつかの種類の飲み薬や注射薬(GLP-1受容体作動薬)があり、自身に合うタイプや量を決めていきます。
1型糖尿病・薬物療法が不十分な2型糖尿病・血糖値を下げる薬を使用できない妊娠糖尿病では、人工的にインスリンを補われます。
インスリンの投与は「自己注射」によって行われ、治療のほかにも厳密な食事管理なども必要です。
このように糖尿病にはいくつかのタイプがあり、免疫の異常による1型糖尿病を予防する方法は現時点ではないとされています。
一方、生活習慣が関わる2型糖尿病や妊娠糖尿病は問題となる生活を改善することで発症や悪化をある程度予防することが可能です。
規則正しい食生活、運動を心がけ、ストレスや喫煙習慣など生活上の習慣に注意するようにしましょう。